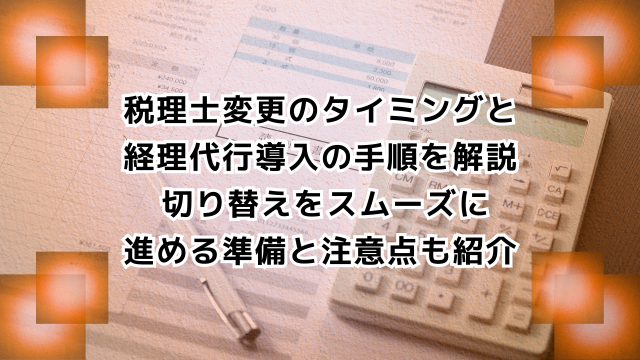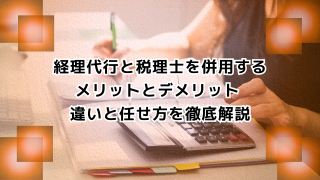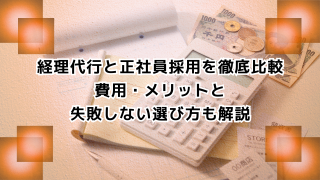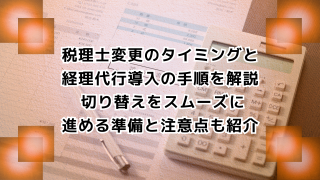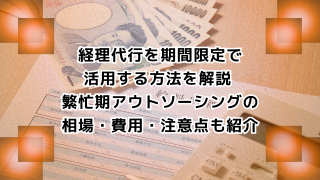経理担当者の退職や採用難が続き、「人手が足りず業務が回らない」と悩む企業が増えています。このまま放置すると、決算や税務対応に支障をきたす可能性も。本記事では、外注とDXの活用によって経理の人手不足をどう乗り越えるかを具体的に解説します。

経理の人手不足が起きる主な原因と背景
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 採用難と人材流出の二重苦
- 属人化と非効率な業務フロー
- 会計・管理の範囲が広がっている現状
以上のポイントを踏まえると、経理部門の人手不足は単なる人材不足ではなく、組織構造や業務のあり方にも深く起因していることがわかります。ここでは、それぞれの要因について詳しく解説します。
採用難と人材流出の二重苦
近年、経理人材の採用は非常に困難を極めています。求人数に対して応募が少なく、さらに専門性が求められるため即戦力の確保が難しいという課題があります。ようやく採用できたとしても、労働条件や働き方に満足できない場合、すぐに離職するケースも少なくありません。
特に中小企業では、給与水準やキャリアパスの面で大手企業に劣る傾向があり、優秀な経理人材を維持することが困難です。このような採用難と人材流出が重なることで、慢性的な人手不足が発生し、経理・会計・管理といった重要な業務の継続が危ぶまれる状況になります。
属人化と非効率な業務フロー
多くの企業では、経理業務が特定の担当者に依存しており、「その人しか分からない」属人化が問題となっています。こうした体制では、担当者が急に退職・休職した際、業務が一時停止し、ミスや漏れが発生するリスクが高まります。
また、手作業が多く、業務フローが標準化・効率化されていない企業では、同じ処理に余分な時間と労力がかかり、限られた人員では対応しきれない状況が生まれます。こうした背景も、人手不足の深刻化に拍車をかけています。
会計・管理の範囲が広がっている現状
近年の経営環境では、単なる仕訳や帳簿付けにとどまらず、予算管理・資金繰り・税務対応・内部統制など、経理・会計・管理に求められる役割が広がっています。業務量が増加する一方で人員補充ができていない場合、現場は常にキャパオーバーの状態になります。
さらに、ITや法令の変化に対応するために、新たな知識やスキルが求められる点も、経理人材にとって大きなプレッシャーです。こうした構造的要因が積み重なり、経理部門の人手不足は深刻な問題へと発展しています。
経理業務が回らないときに発生する3つのリスク
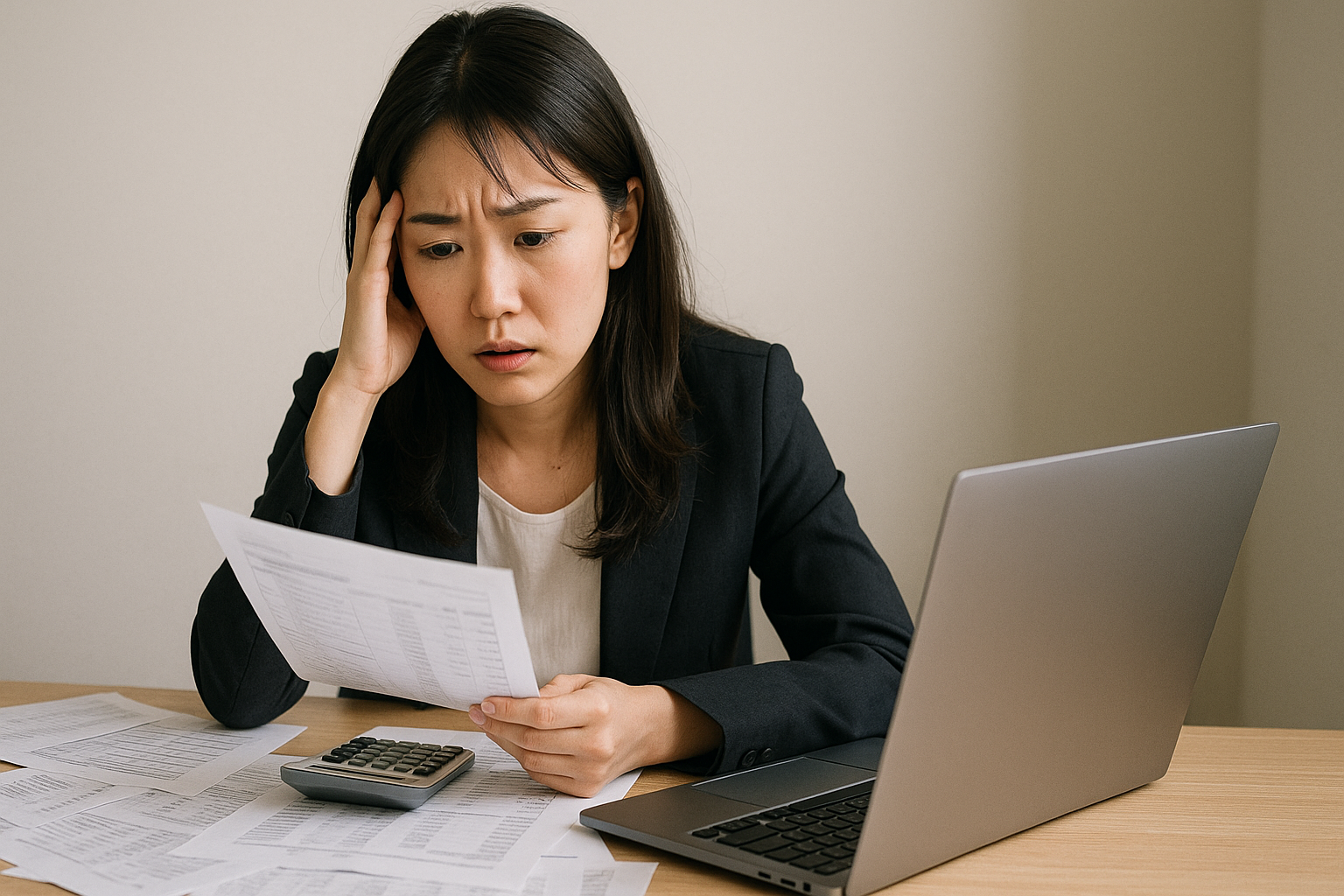
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 月次・年次決算の遅延と税務対応への影響
- 支払漏れや債権管理の不備
- 社内業務全体への波及と信頼低下
経理業務が滞ることで発生するリスクは、単なる業務遅延にとどまりません。会計の信頼性低下、資金繰りの悪化、社内外の信用喪失など、企業経営全体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。それぞれのリスクについて詳しく見ていきましょう。
月次・年次決算の遅延と税務対応への影響
経理部門の人手が不足すると、決算業務の処理が遅れ、月次・年次決算の締めが間に合わなくなるケースが増えます。特に年次決算は、法人税申告や金融機関への報告に直結するため、遅延による影響は大きくなります。
税理士とのやりとりもスムーズに進まなくなり、申告期限に間に合わないリスクが発生します。こうした事態を避けるには、経理・会計処理を計画的かつ継続的に進める体制の整備が不可欠です。
支払漏れや債権管理の不備
人手不足により、請求書処理や支払予定の管理が後回しになると、支払漏れ・遅延が発生するリスクが高まります。これにより、取引先との信頼関係が損なわれるだけでなく、取引停止などの事態にもつながりかねません。
一方で、売掛金の回収漏れや督促の遅れも発生しやすくなり、債権管理が甘くなることでキャッシュフローに影響を及ぼします。経理・管理の精度が企業の資金繰りを左右する重要な要素であることがよく分かります。
社内業務全体への波及と信頼低下
経理業務は、給与計算、予算管理、経営数値の可視化など、他部門との連携が必要な業務も多く含まれます。そのため、経理が機能不全に陥ると、社内の業務全体に支障が及ぶことがあります。
たとえば、予算の進捗確認ができず意思決定が遅れる、人件費の管理が不十分で採用計画がずれるといった影響が出ます。こうした連鎖的な問題が積み重なると、経営陣や従業員の間に「この会社は大丈夫か?」という不信感が広がることにもなりかねません。
人手不足の経理を救う2つの対策
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 外注によるリソース補完
- DXツールでの業務効率化
経理部門の人手不足に対しては、「人を増やす」だけでなく、仕組みや外部リソースを活用する戦略的な視点が重要です。ここでは、すぐに実行可能な2つの対策を紹介します。
外注によるリソース補完
経理業務の外注は、慢性的な人手不足を解消する有効な手段です。記帳代行や支払管理、会計ソフトの入力作業など、定型業務を外部に委託することで、社内スタッフの負担を軽減できます。
特に、専門知識が必要な処理を信頼できる外注先に任せることで、業務の正確性と効率性が向上します。また、育成コストや採用リスクを抑えながら、必要な業務だけを柔軟に依頼できる点も中小企業にとっては大きなメリットです。
DXツールでの業務効率化
経理・会計・管理業務のDX(デジタル・トランスフォーメーション)も、人手不足対策として非常に有効です。たとえば、クラウド型会計ソフトの導入により、仕訳処理やレポート作成が自動化され、人的作業が大幅に削減されます。
さらに、経費精算や請求書発行をデジタル化することで、ペーパーレス化が進み、在宅勤務との相性も良くなります。一人ひとりの業務効率を最大化することで、限られた人員でも経理機能を安定的に維持できるのです。

外注とDXを組み合わせたハイブリッド型が最適な理由
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 経理・会計・管理すべての最適化が可能
- コストと品質のバランスを両立できる
単独での外注やDX導入だけでは限界があります。人の力とテクノロジーの両方を活用するハイブリッド型の導入こそ、経理の人手不足解決に最も現実的かつ持続可能なアプローチといえるでしょう。以下でその理由を解説します。
経理・会計・管理すべての最適化が可能
外注は人手不足を補う手段であり、DXは業務そのものを効率化する技術です。これらを組み合わせることで、経理・会計・管理の各業務をシームレスに最適化できます。
例えば、日常の仕訳や支払処理はクラウドツールで自動化し、判断や監査が必要な部分は外部の専門家に任せるといった分業体制が実現可能です。これにより、内部人員はコア業務に集中でき、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。
コストと品質のバランスを両立できる
ハイブリッド型の最大のメリットは、コストと業務品質のバランスを取れることです。すべてを内製化しようとすると高コストになり、すべてを外注すると業務コントロールが難しくなります。
その点、外注とDXを組み合わせれば、定型業務はツールで削減し、判断力を要する業務だけを外注することで、必要最小限のコストで最大限の成果を得ることが可能です。限られたリソースで質の高い経理体制を維持できるため、安定経営にも直結します。
- 経理の人手不足は「採用難+退職リスク+業務過多」による複合的課題
- 属人化や非効率な業務が、人手不足の影響をさらに深刻化させる
- 業務停滞によるリスクは、決算遅延・支払漏れ・社内信頼の低下など多岐に及ぶ
- 外注とDXは、それぞれ異なる課題を補完しあう効果的な対策
- ハイブリッド型の導入により、業務の最適化とコスト効率を同時に実現可能
経理の人手不足は、いまやどの中小企業にとっても無視できない経営課題です。今こそ、「人材依存からの脱却」と「業務の仕組み化」に取り組むタイミングです。
まずは外注やDXの導入について、専門家に相談するところから一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。