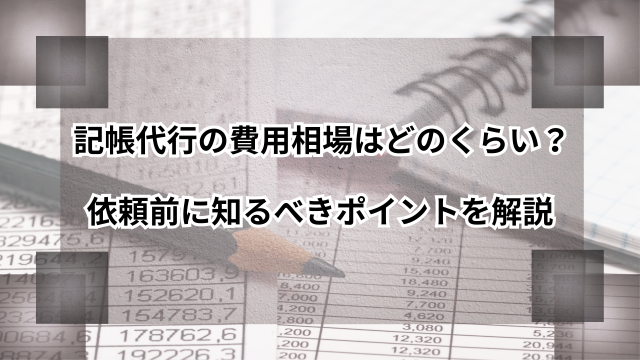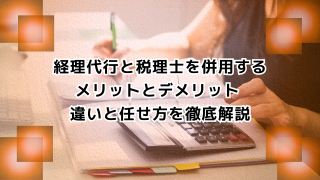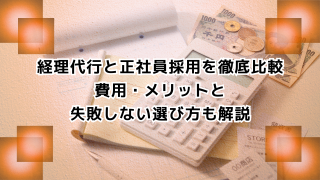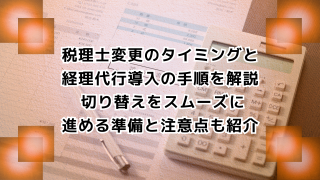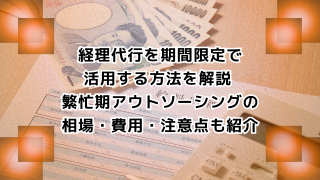経理を外注することで、経営資源をコア業務に集中させる企業が増えています。実際にどれくらいの費用がかかり、どのような業者を選ぶべきか。この記事では、経理外注の基礎から実践までを網羅的にお伝えします。

経理を外注する前に知っておきたい3つの基礎知識
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 経理外注とは?社内経理との違い
- どんな業務を外注できるのか?
- 経営視点で考える外注のメリットと注意点
経理を外部に委託する際には、事前に知っておくべき基本的な考え方があります。社内と外注の違い、外注可能な業務範囲、経営への影響などを押さえておくことで、より的確な判断ができるようになります。この章では、経理外注の前提として必要な基礎知識を整理して解説します。
経理外注とは?社内経理との違い
経理外注とは、自社の経理業務の一部または全部を外部の専門業者に委託することを指します。これにより、企業は経理部門を社内で抱えずに済み、リソースを効率的に配分できるようになります。社内経理では担当者の採用・育成・管理が必要ですが、外注ではその必要がなく、専門性の高い業務を一定の品質で実行してもらえます。
また、社内経理では退職や休職による業務停滞リスクがありますが、外注ではチーム体制での対応が一般的で、安定性が高い点もメリットです。経理に関する人的リスクを減らしたい経営者にとって、有力な選択肢となるでしょう。
どんな業務を外注できるのか?
経理外注では、業務範囲を柔軟に設定できます。具体的には、以下のような業務が外注対象となります。
- 日々の仕訳入力や記帳業務
- 請求書・領収書の管理と発行
- 経費精算の処理
- 月次決算や年次決算の補助
- 銀行振込データの作成や支払管理
- 税理士とのやりとりや資料提出の補助
このように、ルーチン業務から決算支援まで多岐にわたる業務を外注可能です。業務の一部をアウトソーシングし、社内では経営判断や戦略的な会計管理に集中するというスタイルも有効です。
経営視点で考える外注のメリットと注意点
経営の視点から見た経理外注の最大の利点は、リソースの最適化と業務の標準化です。専門業者に任せることで、経理品質を維持しつつ自社のコア業務に集中できます。特に成長フェーズにある企業や経理人材の確保が難しい業種では、外注による安定運用が経営効率を高めます。
一方で、注意すべき点もあります。たとえば、外注先との情報共有が不十分だと、業務に齟齬が生じるリスクがあります。また、自社に会計知識が全くないと、業者任せになりすぎて経営判断に影響を及ぼす恐れもあります。外注を成功させるには、一定の経理リテラシーを保ちながら、パートナーとして連携できる体制が必要です。
経理外注で業務が変わる3つのメリット

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 本業に集中できる体制がつくれる
- 経理ミスや属人化リスクの軽減
- 経営データの可視化と意思決定のスピードアップ
経理を外注することによって、企業の業務体制や経営の質に大きな変化がもたらされます。単なる作業の代行にとどまらず、経営効率やリスクマネジメントにまで影響するのが、経理外注の大きな特徴です。この章では、経理外注によって得られる具体的なメリットを3つの視点から解説します。
本業に集中できる体制がつくれる
経理業務は地味で煩雑ながらも、正確性と継続性が求められる作業です。これを社内で担う場合、人的リソースや教育に多くの時間を割かれ、本来の事業活動に集中できないという課題が生じます。
外注により経理作業を任せることで、経営者や幹部、担当者の時間を本業に振り向けることが可能になります。特に中小企業やスタートアップでは、限られた人的資源を最大限活用することが重要です。経理の外注は、社内のリソースを事業成長に直結する領域に集中させる手段として有効です。
経理ミスや属人化リスクの軽減
経理業務を特定の社員に依存していると、その人が休職・退職した場合に業務が停滞してしまうことがあります。また、業務内容がブラックボックス化しやすく、ミスが見逃されるリスクもあります。
外注化すれば、標準化されたプロセスに基づいたチェック体制が敷かれているため、ミスの早期発見や再発防止が可能です。さらに、複数人のチームで業務を管理するケースも多く、属人化リスクが大幅に下がります。これにより、経営の安定性も向上します。
経営データの可視化と意思決定のスピードアップ
正確な経理データを迅速に揃えられれば、経営判断の材料として大きな力を発揮します。外注業者は帳簿の整備だけでなく、月次決算レポートやキャッシュフロー表の作成など、経営分析に役立つ資料を提供してくれることがあります。
これにより、資金繰りや投資判断といった意思決定をスピーディに行えるようになり、経営のスピード感が高まります。また、客観的な第三者視点からのフィードバックも得られるため、自社の財務状況を俯瞰する視点が育ちます。

経理外注の料金相場と費用の内訳を徹底解説
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 基本的な料金体系(月額制・業務単位)
- 依頼する業務内容ごとの相場感
- 経理外注にかかる費用とコスト削減効果のバランス
経理業務を外注するにあたり、費用面での不安や疑問を持つ方は少なくありません。料金体系や業務ごとの相場感を正しく理解しておくことは、無駄な出費を防ぐためにも非常に重要です。この章では、経理外注の一般的な価格設定や費用の内訳について詳しく解説します。
基本的な料金体系(月額制・業務単位)
経理外注の料金体系は、大きく分けて「月額固定制」と「業務単位制」の2つがあります。
- 月額制:毎月一定の料金で、事前に決めた範囲の業務を一括で依頼する形式。継続的な業務が多い企業に適しています。
- 業務単位制:記帳代行や請求書発行など、作業内容ごとに料金が発生する形式。スポットでの依頼や業務量が変動する場合に向いています。
どちらの方式を選ぶかは、外注する業務の内容や企業の経営スタイルに応じて決めるのが一般的です。
依頼する業務内容ごとの相場感
実際にかかる費用は、依頼する業務の種類と量によって異なります。以下に代表的な業務とその相場感をまとめます。
| 業務内容 | 相場(税抜) |
| 記帳代行 | 月5,000〜30,000円程度 |
| 請求書・領収書発行 | 1通100〜300円 |
| 経費精算のチェック | 月5,000〜15,000円程度 |
| 月次決算補助 | 月10,000〜50,000円以上 |
| 年次決算書類の作成 | 年50,000〜150,000円程度 |
※業種・取引件数・処理量によって大きく変動します。詳細は個別見積もりが基本です。
経理外注にかかる費用とコスト削減効果のバランス
一見すると外注費用は高く感じられるかもしれませんが、社内で経理担当者を雇う場合の人件費・教育コスト・管理負担を考慮すると、外注はコストパフォーマンスに優れる場合が多くあります。
例えば、月5万円の外注費用であっても、フルタイム社員1名の雇用コスト(社会保険料・交通費・福利厚生を含めた月額25万円以上)と比較すると、大幅な節約になります。また、業務効率の向上による間接的な利益も無視できません。
このように、経営全体を俯瞰して判断することで、経理外注は「コスト」ではなく「投資」と捉えることができるようになります。
外注先選びで失敗しないための3ステップ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 自社の業務範囲と外注目的を明確にする
- 比較すべきポイントと選定基準
- 経営視点で考える「信頼できるパートナー」とは?
経理業務を外注する際、どの会社に依頼するかは経営の安定性に直結する重要な判断です。料金や実績だけでなく、自社との相性や業務理解度も慎重に見極める必要があります。この章では、失敗しない外注先選びのために押さえるべき3つのステップを解説します。
自社の業務範囲と外注目的を明確にする
まず最初に行うべきは、外注の目的と自社が委託したい経理業務の範囲をはっきりさせることです。たとえば「記帳だけ任せたい」のか、「月次決算まで対応してほしい」のかで、適した業者は大きく変わります。
業務内容を明確にする際は、次のポイントを整理しましょう。
- 現在社内で行っている経理業務の一覧
- 外注したい業務とその理由
- 外注により得たい成果(例:ミス削減、時間確保、経営効率化)
目的が曖昧なまま依頼すると、想定外の業務が残ったり、成果に不満を感じる可能性があります。事前の整理が非常に重要です。
比較すべきポイントと選定基準
外注先を選ぶ際は、複数社を比較検討し、定量・定性的な観点から判断することが求められます。見るべきポイントは以下のとおりです。
- 料金体系と費用対効果
- 提供可能な業務範囲と柔軟性
- 担当者の対応スピードと説明力
- 経理に関する知識の深さ・経験値
- 自社の業種に対する理解度
また、問い合わせ時の対応姿勢やヒアリング内容からも信頼度がうかがえます。形式的な情報だけでなく、やりとりの中で感じる印象も大切にしましょう。
経営視点で考える「信頼できるパートナー」とは?
単に経理作業をこなしてくれるだけでなく、経営を支える視点を持った外注先こそが「本当に信頼できるパートナー」です。経営者にとって、数字の正確さだけでなく、それをもとにした助言や提案ができる存在は非常に貴重です。
たとえば、経営状況に応じたキャッシュフロー管理や、今後の資金計画のアドバイスをしてくれる外注先であれば、単なる事務代行を超えた価値を提供してくれます。
このような視点で外注先を選ぶことで、経理業務は単なるコストではなく、経営強化のための「戦略的アウトソーシング」となります。
経理外注に関するよくある疑問と不安の解消
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 外注先にどこまで任せていいの?
- 情報漏洩やトラブルが起きたら?
- 税理士との役割分担はどう考えるべき?
経理を外注したいと思っていても、不安や疑問が障壁となって踏み出せない経営者は少なくありません。この章では、よく寄せられる3つの疑問を取り上げ、具体的な解決策を交えて解説します。
外注先にどこまで任せていいの?
経理業務の外注範囲は柔軟に設定できますが、「どこまで任せるべきか」の判断は慎重に行う必要があります。一般的には、以下のような分担がよく見られます。
- 外注に任せる業務:記帳、請求書管理、支払処理、月次資料作成などの定型業務
- 社内で行う業務:支払承認、重要な経営判断に関わる会計方針の決定など
全てを外注に任せることは可能ですが、経営者自身が数字に無関心になってしまうと本末転倒です。信頼できる業者に実務を委ねつつ、自社内では意思決定に必要な情報を把握しておく体制づくりが求められます。
情報漏洩やトラブルが起きたら?
経理情報には、銀行口座、取引先情報、従業員の給与など、極めて機密性の高いデータが含まれます。外注にあたって情報漏洩のリスクを懸念するのは当然です。
しかし、信頼できる外注先であれば、以下のようなセキュリティ対策が講じられています。
- NDA(秘密保持契約)の締結
- データ送信時の暗号化やクラウド管理体制
- 社内におけるアクセス権限管理と監査体制
トラブル時の対応についても、業者のサポート体制や保険加入状況を事前に確認することで、安心材料となります。契約時には、トラブル時の責任範囲を明文化しておくことが重要です。
税理士との役割分担はどう考えるべき?
経理業務の外注と税理士の業務は、重なる部分もありますが明確に異なる役割を持っています。
| 役割 | 経理外注(代行業者) | 税理士 |
| 記帳・領収書整理 | ◯ | △(必要に応じて) |
| 決算補助 | ◯ | ◯ |
| 税務申告書の作成 | ✕ | ◯(専門領域) |
| 税務調査の対応 | ✕ | ◯ |
| 経営コンサル | △(業者による) | ◯(顧問契約により) |
多くの企業では、「日々の業務は経理代行に任せ、税務関係は税理士に依頼する」といった形で分業しています。双方の役割を正しく理解し、連携が取れるようにすることで、スムーズな経営管理が実現します。
- 経理外注とは、社内経理業務を外部業者に委託する手法であり、業務効率と経営資源の最適化に貢献する。
- 外注できる業務範囲は幅広く、記帳や請求書発行から月次決算補助まで対応可能。
- 費用は業務内容や依頼形態によって異なるが、月額制や業務単位制が一般的で、コスト削減効果も高い。
- 外注先の選定には、自社の目的整理・比較検討・経営視点からの信頼性評価が不可欠。
- 情報漏洩リスクや税理士との分担についても、事前の確認と適切な契約で不安を軽減できる。
経理外注は、単なる作業代行ではなく、経営効率を高めるための重要な手段です。コスト面の不安や外注先選びの難しさもありますが、ポイントを押さえて判断すれば、あなたの企業にとって最良のパートナーを見つけることができるはずです。